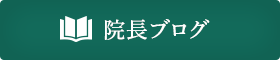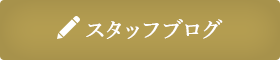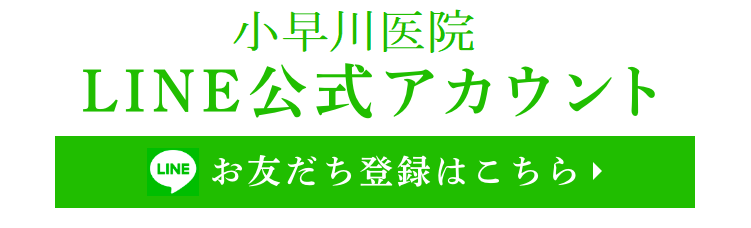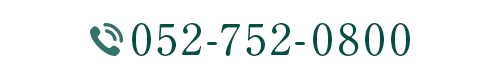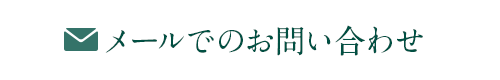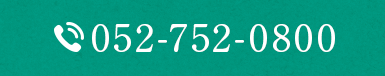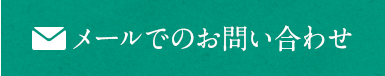2014.11.30更新
認知症の講演会を開催しました
11月29日土曜日の午後、筑波大学医学部(産学リエゾン研究センター)准教授の内田和彦先生と株式会社MCBI取締役の渕木幹男さんを講師にお招きして、認知症に関する院内講演会を開催しました。
今回は「認知症と軽度認知障害(MCI)について」というテーマでお二人からお話を伺いました。
アルツハイマー型認知症では、アミロイドβという物質が発症の20年近く前から徐々に脳細胞に蓄積し始めます。
内田先生は、同じ筑波大学医学部の精神科の朝田 隆教授らとの共同研究で、この物質の脳細胞外への排出の過程にかかわる3種類のたんぱく質を発見しました。そして、これらのたんぱく質の血液中の濃度の変化を調べることにより、認知症の予備軍である軽度認知障害(MCI)になっているかを判定する方法(MCIスクリーニング検査)を開発しました。この方法は10cc程度の採血で簡単にできるのが特徴です。
この検査法を実用化するために、内田先生は渕木さんらとともに筑波大学発のベンチャー企業MCBIを立ち上げました。
先生は「MCIを放置すると4年で約半数が認知症になるので、このMCIスクリーニング検査などで早期に発見し、運動や食事療法、脳トレ、高血圧・糖尿病のコントロール、サプリメントなどで認知症の発症を予防することが重要だ」強調されました。
講演後、参加者から多くの質問が寄せられ、認知症に対する関心の高さがうかがわれました。
このMCIスクリーニング検査は当院でも実施しています。興味のある方は遠慮なくご相談ください。
2014.11.28更新
認知症勉強会が長久手南クリニックで開催されました
11月26日の夜、認知症専門の在宅医療で有名な岩田 明先生が院長をされている長久手南クリニックで、認知症の勉強会が開催され、コウノメソッドの提唱者である河野和彦先生が講演されました。介護職・患者さんのご家族・認知症に携わっている医師など50名ほどの参加者があり、会場は超満員となりました。
河野先生のお話を伺うのは、今年の夏以来4か月ぶりですが、この間にコウノメソッドが大きく進化しているのに驚かされました。
今回の講演の特徴は、アルツハイマー型認知症、レビー小体型認知症、前頭側頭葉変性症などの変性系の認知症の診断、治療にとどまらず、進行性核上性麻痺(PSP)、多系統萎縮症(MSA)、皮質基底核変性症(CBD)などの神経変性疾患や自閉症、線維筋痛症などの診断・治療についてもわかりやすく解説されたことです。
これらの治療で共通の武器となるのがグルタチオン点滴療法です。パーキンソン病の治療から始まったグルタチオンの臨床応用がいろいろな分野に広がっていくという、非常に夢のある話でした。
河野先生の「患者さんもその家族もともに救う医療」がいよいよ完成の域に達してきたと感じました。
2014.11.16更新
認知症についての市民シンポジウムに参加しました
千種区の認知症地域連携の会が主催する「2014年度市民シンポジウム」が、11月15日に千種区役所の講堂で開催されました。
アメリカの国立加齢研究所(NIA)が (1)地中海式食事 (2)認知活動 (3)運動が認知症を抑制すると発表したのに対応して、今回のシンポジウムでは栄養、認知活動、運動のそれぞれの専門家がシンポジストとして登場し、認知症予防のための対策を議論しました。この中で、有酸素運動、特にダンスが認知症を予防する効果があること、簡単な計算をテンポよく行う訓練によって、脳の司令塔である前頭前野を含む脳全体が活性化し、認知症予防につながることが印象に残りました。
また筑波大学教授の朝田 隆先生が「認知症の早期発見と予防」というテーマで基調講演をされました。
筑波大学では、軽度認知機能障害(MCI)と診断された患者さんに対して、「認知力アップデイケア」を行い、大きな成果を上げています。これは、体操・ボール運動・ストレッチなどの軽い運動で構成された運動メニュー、認知ゲームによる認知トレーニング、美術・音楽などの創作活動を通じて脳を鍛える芸術療法、古いテレビの映像を用いた回想法を組み合わせた認知症予防プログラムです。MCIの患者さんたちが、このプログラムを通じて生き生きと認知症予防に励んでいる姿が動画で映し出され、非常に感銘を受けました。
当院でも、芸術療法を用いた認知力アップデイケアの実施に向けて準備中です。詳細が決まりましたら当ホームページでもお知らせしますので、お楽しみに・・
2014.11.11更新
洪尚樹先生の糖尿病講演会に参加しました
先日名古屋観光ホテルで、我が国の糖尿病治療のオピニオンリーダーとして有名な洪尚樹先生が「これからの糖尿病治療」というタイトルで講演され、私はその座長を務めさせていただきました。私が最も尊敬する糖尿病専門医の一人である先生の講演会の司会をさせていただいた事は、私にとっては光栄の至りでした。
洪先生のお話を初めて伺ったのは10年以上も前のことです。当時はまだSU薬が糖尿病薬物療法の主流でしたが、先生はこのころから「低血糖を起こさない治療」の重要性を強調され、インスリン抵抗性改善薬を糖尿病の薬物治療の中心に据えることを提唱されていました。低血糖によって心血管イベントが増えたり認知症のリスクが高まったりすることが明らかになった今、この当時の先生のお考えがいかに卓見であったかがよくわかります。
今回の講演でも、インスリン抵抗性改善薬が治療の中心であることには変わりはありませんでしたが、治療の目標が、三大合併症(神経障害、網膜症、腎症)の予防から動脈硬化による心血管イベント(脳卒中、狭心症、心筋梗塞、閉塞性動脈硬化症)の抑制に移り変わっていることを強調されていました。
洪先生の最新の糖尿病治療戦略を知ることができた大変有意義な講演会でした。
ARTICLE
SEARCH
ARCHIVE
- 2024年3月 (1)
- 2024年1月 (3)
- 2023年11月 (1)
- 2020年4月 (2)
- 2018年8月 (1)
- 2017年1月 (1)
- 2016年7月 (2)
- 2016年6月 (4)
- 2016年4月 (1)
- 2016年2月 (2)
- 2016年1月 (4)
- 2015年12月 (2)
- 2015年11月 (3)
- 2015年5月 (6)
- 2015年4月 (5)
- 2015年3月 (1)
- 2015年2月 (5)
- 2015年1月 (4)
- 2014年12月 (3)
- 2014年11月 (4)
- 2014年10月 (5)
- 2014年9月 (3)
- 2014年8月 (6)
- 2014年7月 (6)
- 2013年12月 (3)
- 2013年11月 (7)
- 2013年10月 (8)
- 2013年9月 (7)
- 2013年8月 (8)
- 2013年7月 (7)
- 2013年6月 (6)
- 2013年5月 (8)
- 2013年4月 (5)
- 2013年3月 (5)
- 2013年2月 (8)
- 2013年1月 (8)
- 2012年12月 (8)
- 2012年11月 (7)
- 2012年10月 (6)
- 2012年9月 (5)
- 2012年8月 (5)
- 2012年7月 (17)
- 2012年6月 (9)
- 2012年5月 (9)
- 2012年4月 (4)
- 2012年3月 (14)
- 2012年2月 (7)
- 2012年1月 (4)
- 2011年12月 (4)
- 2011年11月 (1)